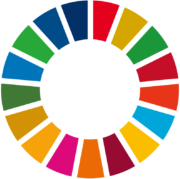熟年離婚の財産分与はどうなる?専業主婦や年金問題について | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
COLUMN
不動産売却コラム
熟年離婚の財産分与はどうなる?専業主婦や年金問題について
「熟年離婚で家を売る際の注意点は?」「何を意識すれば良いの?」熟年離婚を検討している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では熟年離婚における財産分与の特徴やリースバックのメリット、デメリットについて紹介しています。
この記事を読めば、熟年離婚で家を売る際の注意点について網羅できますので、是非ご一読ください。
そこで、今回の記事では熟年離婚における財産分与の特徴やリースバックのメリット、デメリットについて紹介しています。
この記事を読めば、熟年離婚で家を売る際の注意点について網羅できますので、是非ご一読ください。
目次
熟年離婚における財産分与の特徴

熟年離婚における財産分与は、長期間の婚姻によってさまざまな財産が対象となり、その金額も高額になることがあります。しかし、適正な財産の開示や評価が難しく、公平性を求めてトラブルが発生することもあるでしょう。
また、高齢の夫婦にとっては、今後の生活や相続についても重要な話し合いが必要です。十分な財産がある場合は問題ありませんが、そうでない場合は将来の生活手段などについて合意し、財産分与の割合を変更する必要があります。
熟年離婚における財産分与は、話し合うべき内容が多く、円満な解決をするためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
財産分与の方法
清算的財産分与婚姻期間中に夫婦が共同で所有する預貯金、不動産、有価証券などの財産は、基本的には2分の1ずつ分割されることを指します。この財産分与は、財産の名義や離婚の原因に関わらず、財産分与の中核となる分割方法です。
扶養的財産分与
離婚により、夫婦のどちらかが経済的に困難な状況となった場合、その配偶者の生活を支援する目的で財産を分割することを指します。具体的な例として、高齢や病気のために安定した収入を得ることが難しい場合などに認められることがあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料は財産分与とは異なる性質を持つため、一般的には別々に算出して請求します。ただし、慰謝料と財産分与はどちらも金銭的な問題であるため、厳密に区別せずにまとめて財産分与することも可能です。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。例えば専業主婦の妻でも、家事や夫の支えをしていたという観点から、収入の有無に関わらず2分の1の割合で財産分与が行われます。ただし、夫婦間の話し合いで割合を変更することも可能です。また、以下のケースでは割合が変わる可能性があります。
・自身の努力で医師や弁護士などの資格を取得し、財産を築いた場合
・歌手や俳優、アーティストなど特別な才能によって財産を築いた場合
・夫婦の一方が著しく浪費していた場合
財産分与の請求期間は2年
財産分与に関しては、離婚後の請求期限が存在します。具体的には「離婚から2年以内」が請求の期限となります。この期限を過ぎると、基本的には財産分与を請求することはできません。そのため、離婚が決まったらできるだけ早く財産分与について話し合いを進めるのが良いでしょう。もし夫婦間で合意が成立しない場合は、家庭裁判所などで調停を行い、問題を解決する手続きを取ることもあります。調停の手続きが進行中であれば、2年を過ぎていても請求権は継続します。話し合いが難航している場合は、この方法を利用して時間を延ばすことも有効な手段と言えるでしょう。ただし、2年以内であっても、双方が合意のもとで財産分与を行うことは可能です。
年金分割

熟年離婚では、年金の分与が特に注目されるポイントです。婚姻期間中に専業主婦として過ごし、配偶者の収入に頼って生活していた人は、離婚後の収入や年金について心配することもあるでしょう。このような場合に役立つ制度が年金分割です。
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金を分割し、それぞれが自身の年金として受け取る制度です。この制度には、年金を公平に受け取ることができるメリットがあり、離婚後も安定した生活を築くことができます。
合意分割
合意分割は、夫婦間の協議に基づき保険料の分割割合を決めるか、裁判所によって分割割合を決定してもらう方法です。割合の上限は2分の1とされており、請求期限は原則として離婚後の翌日から2年間となっています。合意分割の条件は以下の通りです。
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
3号分割
3号分割は、夫婦のどちらかが第3号被保険者である場合に適用される年金分割の制度です。配偶者が第2号被保険者であり、婚姻期間中に厚生年金を支払っていた場合、相手の合意がなくても自動的に第3被保険者が2分の1の保険料を支払ったと見なされます。3号分割の条件は以下の通りです。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
親権や相続について

両親が離婚すると、父親と母親は互いに配偶者ではなくなるため、相続人ではなくなりますが、法律上では、子どもは両親の相続人となります。例えば、子どもが幼い頃に両親が離婚し、片方の親とは長い間会っていなかったとしても、子どもは父親と母親の両方の相続人となり、両親の財産を相続することになります。
親権にかかわらず相続人となる
両親が離婚した後、子どもが相続人となる点については、両親が親権者であるかどうかは関係ありません。親権とは、未成年の子どもが教育や監護を受け、財産も守られるための権限や義務のことです。日本の法律では、両親が離婚する場合、父親と母親のどちらかが子どもの親権者となります。親権者となった親は、子どもと一緒に生活することが一般的であり、親権者でない親と子どもの接触は少なくなることが多いです。しかし、相続においては、子どもは親権に関係なく実親の相続人となります。
子どもが戸籍から抜けても相続人になる
両親が離婚すると、両親は別々の戸籍になります。子どもの戸籍に関しては、親権者がどちらかに関係なく、元の戸籍に残りますが、母親が親権者であり旧姓に戻る場合、子どもの姓が母親と異なることを避けるため、子どもを母親の戸籍に移すことが一般的です。離婚後に子どもの戸籍を親の戸籍から抜いたとしても、将来的に子どもは父親や母親の相続人となります。親が再婚した場合
両親が離婚し、母親が再婚して子どもが再婚相手と普通養子縁組をした場合でも、子どもは実の親の相続人となります。子どもは実の親である父親や母親の相続人になるだけでなく、再婚相手の相続人にもなります。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、特別養子縁組の場合、子どもと実の親の親子関係が断たれるため、実親の相続人でなくなる点には注意が必要です。ただし、再婚の場合、特別養子縁組が裁判所で認められることは稀で、子どもと再婚相手は普通養子縁組をするケースが一般的です。
代襲相続に注意が必要
代襲相続とは、相続人よりも先に相続すべき人が亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続人となることを指します。例えば、祖父が亡くなった場合、先に父親が亡くなっていたとすると、祖父の孫にあたる子どもが相続権を取得します。そのため、両親が離婚し、母親に引き取られた場合であっても、子どもは父親の相続人となるだけでなく、代襲相続によって父親の両親の相続人にもなる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、子どもが父親の財産を相続放棄したとしても、その後に父親の両親が亡くなった場合、子どもは代襲相続によって父親の両親の財産を相続する権利が発生します。このような場合、相続したくない場合は再度相続放棄手続きを行う必要があります。
専業主婦の場合

長年の専業主婦としての生活は、経済的自立を困難にする可能性があり、家を売るという決断は大きな影響を及ぼすものです。専業主婦が熟年離婚をする際の確認事項や注意点を紹介します。
離婚時に受け取れる金額の確認
離婚後は、自身の収入や年金で生活していかなければならないため、離婚時にもらえる金額を確認しておくことが重要です。財産分与に関して注意が必要な点は以下の通りです。・相手が財産を隠したり処分したりする可能性があるため、離婚を切り出す前に財産や負債を明確に把握する
・負債も考慮しておかないと結果的に財産分与が減る可能性がある
・別居時の収入は財産分与の対象外となるため、別居はおすすめできない
・相手が財産を処分できないようにするために、裁判所に申し立てることも検討する
年金分割を当てにしないことが大切
先ほど年金分割について解説しましたが、年金分割に頼りすぎるのは賢明ではありません。夫が支払った厚生年金が高額であったり、婚姻期間が長かった場合を除いて、想定よりももらえないことがほとんどでしょう。
どの程度の年金をもらえるのか、正確な金額を把握しておくことが重要です。年金分割だけに頼らず、他の収入源や資産形成にも目を向けることをおすすめします。
リースバックを利用する

熟年離婚の際に家を売る方法の一つがリースバックです。リースバックは、売却した家を買主と賃貸契約を結び、引き続き住み続ける方法です。
リースバックは、熟年離婚において名義変更が難しい場合や、持ち家を売却して現金化したい場合に有効な手段とされています。リースバックを利用する際のメリットとデメリットを紹介します。
リースバックを利用するメリット
家に住み続けられるリースバックを利用する最大のメリットは、自宅に住み続けることができる点です。年を取ってから引越しをするのは精神的にも体力的にも負担がかかりますし、特にお子さんが小さい場合には学校の転校などストレスがかかる可能性もあります。リースバックを利用することで、自宅を売却せずに住み慣れた環境を維持することができます。
ただし、リースバックの契約条件によっては住み続けることが難しいケースもあるため、契約時には条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
引越しの費用と手間がかからない
リースバックを利用すると、引越し費用や手間を節約することができます。通常の売却と異なり、リースバックでは引越しをする必要がありません。引越し費用は時期や荷物の量によって異なりますが、家族で引越しをする場合には数十万円以上かかることもあります。また、引越し後に新しい住まいに必要な家具や家電を購入する費用もかかるかもしれません。リースバックを利用することで、これらの費用を削減できます。
ランニングコストがかからない
リースバックを利用すると、所有権が不動産会社に移るため、固定資産税などのランニングコストの負担がなくなります。固定資産税は不動産の所有者が支払う税金であり、所有権が移ることで固定資産税の支払いが不要になるというメリットがあります。特に地価が上昇し固定資産税が高額になる場合や、相続した不動産の固定資産税が負担になる場合には、リースバックを利用することでランニングコストの軽減が期待できるでしょう。
現金化までの期間が短い
通常の不動産売却では、買い手が見つかるまで現金化することができません。しかし、リースバックの場合は不動産会社が買い取ってくれるため、現金化までの期間が短くなります。すぐにまとまった現金が必要な場合には、リースバックが有効な選択肢となるでしょう。
将来的に買戻しができる
リースバックを利用すると、将来的に売却した不動産を買い戻すことも可能です。例えば、資金繰りが困難になったタイミングで一時的に売却し、将来的に資金繰りが安定した場合に買い戻すことができます。具体的には、相続財産として現金が手に入った時や、同居する子どもの給与が上がり不動産を購入できる信用力が得られた場合などが挙げられます。ただし、リースバックの契約内容によっては再購入ができない場合や、一定期間を空ける必要がある場合もあるため、事前に契約内容を確認しておきましょう。
リースバックを利用するデメリット
所有権移転登記が行われるリースバックを利用する場合のデメリットは、所有権が不動産会社に移ることです。自宅が所有物ではなくなるため、相続時に子どもに譲ることや、不動産を担保に融資を受けることができなくなる可能性があります。
家賃の支払いが発生する
リースバックを利用すると、家賃の支払いが必要となります。家賃は自宅の売却価格に応じて決まり、年間の家賃は利回りや周辺相場によって異なりますが、売却代金の10%程度が相場となります。家賃は相場よりも高めに設定されるため、負担に感じる場合もあるでしょう。また、家の売却費用が高いほど家賃も上昇する傾向があるため、注意が必要です。
住み続けられない可能性がある
リースバックは、ずっと住み続けられない可能性があります。リースバック契約の賃貸期間は契約内容によって異なりますが、通常の賃貸物件と同様に2年の契約期間で更新手続きを行い、ほとんどの場合は住み続けることができます。
しかし、契約内容によっては一定期間しか住むことができない場合もあるため注意が必要です。定期借家契約の場合は、貸主と借主の合意がない限り再契約ができません。
また、家賃の滞納があった場合には、退去を求められることも考えられます。リースバックの家賃は高めに設定されているため、家賃の支払いが困難になれば引越しを余儀なくされる可能性がある点は覚えておきましょう。
買い戻す際の費用が高い
リースバックを利用する際、将来的に売却した不動産を買い戻すことを考える人もいるでしょう。しかし、リースバックでは売却価格が市場価格よりも2〜3割低く設定されているため、買い戻す際の費用は市場価格よりも高くなる場合があります。
買い戻すためには多額の費用がかかることがあるため、費用不足の場合は買い戻しを断念せざるを得ないケースもあるでしょう。
まとめ
今回の記事では、熟年離婚における財産分与の特徴やリースバックのメリット、デメリットについて紹介しました。熟年離婚で家を売る際には、離婚後の収入や相続についても考慮する必要があります。夫婦間で解決ができない場合は、弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。
※こちらの記事は[2024-06-03]時点の記事になり、今後法改正などにより変更になる可能性がございます。