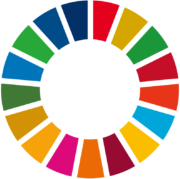離婚時の財産分与で損をしないための基礎知識や注意点 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
COLUMN
不動産売却コラム
離婚時の財産分与で損をしないための基礎知識や注意点
「離婚による財産分与の注意点は?」「名義の問題や不倫の場合はどうしたら良いの?」離婚を検討している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では離婚による財産分与の注意点について紹介しています。
この記事を読めば、離婚による財産分与の注意点について網羅できますので、是非ご一読ください。
そこで、今回の記事では離婚による財産分与の注意点について紹介しています。
この記事を読めば、離婚による財産分与の注意点について網羅できますので、是非ご一読ください。
目次
離婚で財産分与する際の注意点

離婚に伴う財産分与は、多くの人にとって重要な問題です。正確な情報と適切な対応が、円満な離婚協議や裁判での財産分与につながるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅ローンと不動産の名義人が別物であること
不動産の名義と住宅ローンの名義は別物です。つまり、不動産の所有者と住宅ローンの借り主が異なる場合があります。例えば、夫が家の所有者であり、家を購入するために住宅ローンを組んだ場合を考えてみましょう。もし離婚が成立し、妻と子どもが家に住み続けることになった場合、問題が生じる可能性があります。なぜなら、住宅ローンの契約者は夫であり名義人が変わっていないため、妻が家を息子に贈与することができなくなってしまうからです。このようなトラブルを避けるためには、離婚時に不動産と住宅ローンの名義を確認し、必要に応じて変更することが大切です。
財産分与の請求期間が2年以内であること
財産分与に関しては、離婚後の請求期限が存在します。具体的には「離婚から2年以内」が請求の期限となります。この期限を過ぎると、基本的には財産分与を請求することはできません。そのため、離婚が決まったらできるだけ早く財産分与について話し合いを進めるのが良いでしょう。もし夫婦間で合意が成立しない場合は、家庭裁判所などで調停を行い、問題を解決する手続きを取ることもあります。調停の手続きが進行中であれば、2年を過ぎていても請求権は継続します。話し合いが難航している場合は、この方法を利用して時間を延ばすことも有効な手段と言えるでしょう。ただし、2年以内であっても、双方が合意のもとで財産分与を行うことは可能です。
負の財産も財産分与の対象になること
財産分与においては、結婚後に共有した財産だけでなく、負の財産も財産分与の対象です。具体的な例としては、家族や生活費のための借金や、家や車のローンなどが挙げられます。ただし、結婚前に借りた個人的な借金や、結婚後でも個人的に借金をした場合は、財産分与の対象にはなりません。夫婦で共有していたものに対する借金は財産分与の対象となるため、注意が必要です。一例として、夫婦で家族や生活費のために借金をしていた場合が挙げられます。しかし、個人的な娯楽やギャンブルによる借金などは個人の負債とみなされ、財産分与の対象外となります。
住宅ローンを誰が返済するかで揉める可能性がある
住宅ローンの名義人が夫で、家に住み続けるのが妻の場合、誰が住宅ローンの返済をするのかは重要な問題です。家の名義人である夫からすれば、自分が住んでいない家のローンを返済し続けるのは理不尽と感じるかもしれません。一方、妻からすると、家の名義人が夫である以上、住宅ローンの返済を夫に請求したい気持ちもあるでしょう。このような状況は夫婦間での対立を生む原因となり、後のトラブルを生む可能性があります。金融機関からすると、住宅ローンの名義人である夫に対して返済を求めるのが一般的です。しかし、夫が住んでいない家のローンを返済し続けるかどうかは保証できません。そのため、妻が家に住み続ける選択をする際には、住宅ローン返済に関する問題を十分に考慮する必要があります。
住宅ローンの連帯保証人にはリスクが伴う
住宅ローン契約時には、必ず連帯保証人が必要です。一般的には、夫が住宅ローンの名義人となり、妻が連帯保証人となるケースが多いでしょう。しかし、離婚して妻が家を引き継ぎ、夫が住宅ローンの返済を継続する場合、夫が約束を破ってローンの支払いを滞納する可能性もあります。その場合、連帯保証人である妻が住宅ローンの返済をしなければなりません。
このようなリスクを避けるために、住宅ローンの返済を負担しない側は自身が連帯保証人となっていないか確認することが重要です。また、もし連帯保証人として契約して離婚をした場合、連帯保証人を変更する手続きを行うことを検討するのがおすすめです。
夫名義の家は財産分与できる?

離婚における財産分与の際、多くの人が夫名義の家は財産分与できるのか疑問を感じるのではないでしょうか。夫名義の家がどのように取り扱われるのか、注意すべきポイントを紹介します。
財産分与は夫婦で半分ずつになることが多い
離婚においては、財産分与が行われます。夫名義の家であっても、原則として夫婦間で均等に財産を分けることになります。夫が多くのローンを返済していたとしても、財産分与においては夫婦の取り分は均等になることが一般的です。ただし、財産分与の均等な分け方は、家庭裁判所での調停や審判においては「折半を基本とする」とされています。しかし、実際の財産分与では、夫婦の話し合いによって割合を変えることもあり、調停や審判によって特殊な事情や経緯が考慮されて一方に偏った結果になることもあります。
夫婦の取り分の決め方
夫婦の取り分の決め方は、以下の流れで決定することが一般的です。・夫婦間で話し合う
・解決できない場合は離婚調停を申し立てる
夫婦間で話し合う
まず、夫婦間で財産分与について話し合い、共有財産の分け方を決めます。もし夫婦の双方が話し合いによって取り分に合意することができれば、その取り決めに基づいて財産分与を行います。ただし、離婚原因がDVや浮気などの問題がある場合は、慰謝料の請求が認められるため、財産分与が均等に行われるとは限りません。
解決できない場合は離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで財産分与の取り決めができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることがあります。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が関与し、財産分与の方法について話し合います。調停委員からは法的な説明や和解案が示されるため、財産分与が成立しやすくなるでしょう。
ただし、離婚調停においても財産分与が合意されない場合は、最終的には離婚訴訟として裁判官が分配方法を決定することになります。
不倫した相手に財産分与する義務はあるのか

離婚において、不倫をした相手に対して財産分与する義務があるのかは多くの人が疑問に思うことでしょう。不倫した相手への財産分与の有無や条件等を紹介しながら、注意すべきポイントを紹介します。
財産分与の対象となるのは
財産分与の対象となるのは夫婦が協力して築いた財産です。この場合、名義が共同であるか、一方の単独名義であるかは問われません。主な対象としては、預貯金、不動産、有価証券、年金、退職金、家財道具などが挙げられます。また、結婚生活で負債を抱えていた場合でも、それらは財産分与の対象となります。例えば、結婚生活のために組んだカードローンや住宅ローンも、財産分与の対象に含まれるため、注意しましょう。
財産分与の対象外となるのは
結婚前に夫または妻が持っていた財産は、財産分与の対象外となります。また、親から相続した財産も「夫婦が協力して築いた財産」には該当しないため、財産分与の対象にはなりません。個人的な持ち物である服や雑貨なども、財産分与の対象からは除外されます。
さらに、別居期間中に夫または妻がつくった財産も、夫婦が協力して築いた財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。また、個人的な事情で生じた借金も財産分与の対象にはなりません。
原則不倫をした相手にも財産分与する必要がある
基本的には、配偶者が不倫をして離婚の原因を作った場合でも、相手方に財産分与をする必要があります。財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた共有財産を離婚時に分けることによって精算することが目的だからです。そのため、離婚の有責性は財産分与とは別の問題と見なされ、不倫をした配偶者にも財産分与をする必要があるため、注意が必要です。ただし、財産分与には慰謝料的な要素を含めることもあるため、不倫をした配偶者の財産分与額を減額するなど、分与額を調整できる可能性もあります。
注意点としては、不倫によって精神的な損害を受けたとして慰謝料を請求し、財産分与も受け取った場合、慰謝料の要素が既に財産分与に含まれている可能性があることです。
不倫による慰謝料の請求と、財産分与に慰謝料的要素を含めて請求するかどうかを迷った場合は、弁護士等の専門家に相談するのがおすすめです。
協議が決裂したら

離婚において財産分与をめぐる協議が決裂した場合、どのような対応が求められるのか気になる人も多いのではないでしょうか。離婚における財産分与は、離婚前と離婚後で流れが異なるため、それぞれ解説します。円満な解決を目指すためにも、協議が決裂した場合に備えて必要な情報を知っておきましょう。
離婚前の場合
まずは話し合う離婚前に財産分与を決める際には、まずは夫婦で話し合いをする必要があります。話し合いの中で、慰謝料や親権、養育費などの離婚条件とともに、財産分与についても双方が合意できる条件の決定が必要です。双方で合意した場合は、協議離婚合意書を作成し、離婚届を役所に提出することで、協議離婚が成立し、決められた通りの財産を受け取ることができます。
話し合いが決裂したら離婚調停
話し合いが決裂した場合、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行います。離婚調停によって財産分与を含む話し合いが成立すれば、調停離婚が成立し、決められた通りの財産を受け取ることができます。
離婚調停が決裂したら離婚訴訟
離婚調停が決裂した場合は、家庭裁判所で離婚訴訟を起こします。離婚訴訟において財産に関する証明が行われると、裁判官が財産分与の方法を決定し、支払い命令の判決を下してもらうことができます。
離婚後の場合
まずは話し合う離婚後に財産分与を求める場合でも、まずは相手と連絡を取り、夫婦で話し合って財産分与の方法を決める必要があります。話し合いで財産分与に関する条件が双方で合意した場合は、財産分与についての合意書を書面で作成し、合意内容に従って財産を受け取ることができます。
話し合いが決裂したら財産分与調停
話し合いが決裂した場合、家庭裁判所で財産分与調停を行います。財産分与調停では、裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、財産分与についての話し合いを進めることになり、双方が合意すれば調停が成立し、合意内容に基づいて財産を受け取ることができます。
財産分与調停が決裂したら財産分与審判
財産分与調停が決裂した場合、自動的に財産分与審判として進行します。財産分与審判では、審判官が事前に提出された資料などを参考にして、夫婦の財産分与方法を決定します。財産分与審判で決まった内容は判決と同等の効力を持ち、相手が従わない場合は給料や預貯金の差し押さえなどの強制力が働くことになるため、注意しましょう。
同意なく売却されそうになったら

離婚における財産分与をめぐる注意点の一つとして、同意なく財産が売却されそうになるケースがあることです。同意なく財産が売却されそうになった場合に備えて、必要な知識を身につけておきましょう。
売却されてしまうと取り戻すのは困難
夫名義の家が勝手に売却されてしまうと、妻が取り戻すことは非常に困難です。夫名義の家は、元々夫が所有していたことを示す明確な事実であり、夫は権利を持たずに売却したわけではありません。このような場合、合法的な手段で正当な権利者が家を売却しているため、妻が売却自体を取り消すことはできません。そのため、夫婦が別居している状況で夫名義の家が存在する場合、妻が知らないうちに家を売却されないように注意する必要があるでしょう。
同意なく売却されない方法
一度売却されてしまうと取り戻すことは困難ですが、そもそも同意なく売却されないようにする手段があります。事前に対策をしておくことで、住んでいる家を失うリスクを軽減できるでしょう。登記識別情報を預かる
妻が登記識別情報を預かることで同意なく売却されることはなくなるでしょう。不動産を売却する際には、売主が不動産の所有者であることを証明するために登記識別情報が必要です。妻が登記識別情報を預かって別居中の家に保管していれば、夫が同意なく家を売却することが難しくなります。
ただし、再発行ができない場合でも、司法書士が代替の書類を作成することができるため、注意が必要です。
書面で約束をしておく
別居をする際に家を勝手に売却しないという旨を書面に残して約束しておくことも有効な手段と言えるでしょう。売却された場合でも「勝手に売却された場合、売却代金の半額を支払う」という約束をしていれば、夫が家を売却しても、財産分与に基づく請求権を主張することができます。
監視する
夫の行動を注意深く監視することも効果的です。もし、夫が不動産会社に相談して家を売ろうとしている兆候があれば、不動産会社に連絡して離婚協議中である旨を伝えることで販売活動を中止してもらえることがあります。不動産会社も売買のトラブルは回避したいと考えているため、夫の行動を注意深く監視しておきましょう。
仮差押をする
仮差押をすることで法的に勝手に売却されることを防ぐことができます。仮差押は、紛争が解決されるまで一時的に不動産を動かせなくする方法です。不動産が仮差押されると、離婚問題が解決するまで不動産の売却や抵当権設定ができなくなります。不動産に仮差押の登記が行われるため、夫が家を売却しようとしても、不動産会社は売却手続きを進めることができず、買い手を探すことができません。
仮差押の手続きについては裁判所が行いますが、書類作成は弁護士や司法書士に有料で依頼する必要があります。ただし、仮差押のためには財産の約10%を供託金として裁判所に支払う必要があるため、容易に行えるものではない点は覚えておきましょう。
まとめ
今回の記事では、離婚による財産分与の注意点について紹介しました。離婚による財産分与では、家の名義の問題や不倫の問題、財産分与の割合などさまざまな問題が生じることになるでしょう。そのため、離婚後にトラブルにならないように、夫婦間でしっかりと話し合ってから方向性を決定することが大切です。夫婦間での決定が難しい場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。
※こちらの記事は[2024-01-08]時点の記事になり、今後法改正などにより変更になる可能性がございます。